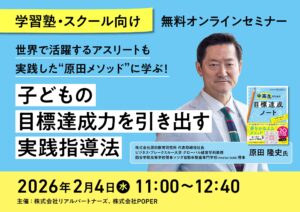高校入試制度が変わろうとしています。
政府が「単願制の見直し」について検討を始めたようです。
<公立高受験「単願制」見直し、複数校の志望可能に>
https://news.yahoo.co.jp/articles/d33ccfa1dc16acbafe05b335ffdcd02dbfedc051
これが実現すれば、公立高校受験において
多くの都道府県で実施されている従来の「1校だけを選び受験する」スタイルから、
「複数校に順位をつけて出願し、希望に応じた学校に割り振られる」スタイルに転換します。
つまり、「どこに出すか」という問題から、
「どう出すか」が重視される時代になるということです。
もちろん、子どもたちにとっては行きたい学校に行ける可能性が高まり、
進路の選択肢も広がるわけですから、趣旨そのものは良いことではないかと思います。
一方で、私がこの変化を最初に聞いたとき頭に浮かんだのは
塾の進路指導を再定義する必要が出てくるということでした。
単願制における従来の塾の進路指導は、
「どの学校なら受かりそうか」という合格可能性の分析と、
「本人の希望」をすり合わせる作業が中心だったと思います。
言い換えれば「確率」に賭ける世界です。
「この学校に本当は行きたいけど、合格率が50%だからちょっと怖い」
「この学校なら80%くらい受かりそうだから、確実に合格するためにはこっちかな」
など、「どの学校を選ぶか」は、
最終的に受かりそうかどうか(=確率)が判断基準の軸になっていたと思います。
もちろん、塾の方針として可能性が低くても生徒さん本人の夢を後押しするケースもあれば、
安全圏を狙う指導をなさるスタンスの塾さんもあるでしょう。
それについての是非は分かれるところでしょうが、
いずれにせよ「確率」が基準になっていることは変わりませんよね。
しかし制度が変われば、その構造も変わります。
生徒さんが希望する学校を複数受験できるようになり、
かつ志望順位がダイレクトに入試結果に反映されるので、
同じような学力の生徒が同じ学校群を受けても、
希望順位のつけ方次第で最終的にどの学校に進学するかは変わる可能性はあるでしょう。
(合格の確率そのものには影響しないでしょうが)
つまり、進路指導は単なる「選択」ではなく、
「順位のつけ方をどう設計するか」という戦略性の要素を帯びてくるのだと言えます。
そうなると塾は、学力の補強者としての存在であることに加え、
「選択のナビゲーター」としての色合いも出していかねばなりません。
見方によっては、中学受験塾の進路指導と近いかもしれません。
私立中学の受験日程は、統一解禁日と解禁2日目の午前入試・午後入試に、
多くの学校が入試日を設定しています。
つまり2日間×午前・午後の2回=4回の入試チャンスで、
どの学校をどう受験するかという組み合わせパターンが大事になってくるわけで、
そうした「戦略性」という点は似ていると思います。
この変化は、中小規模の個別指導塾にとってチャンスかもしれません。
「本人の本当の希望」「家庭の想い」「地域性」まで汲み取った戦略を、
顔の見える距離感で提案できるからです。
例えば生徒さんの高校への志望理由を、
本人に言語化させている塾さんもあるのではないでしょうか。
なぜその学校に行きたいかを深掘りして、それに基づいて志望順位をつけるためでしょうが、
こうしたアプローチはまさに、新しい制度にフィットする進路指導のあり方だと感じます。
一方でそれは、厳しい現実もはらんでいます。
順位づけのアドバイスを塾が行えば行うほど、その“責任”が問われやすくなるからです。
進学後に「やっぱりあっちの学校を第1志望にしておけばよかった」
「塾の先生の言葉を信じたのに」といった声が出るようだと、
塾の信用が揺らいでしまいかねません。
しかもこれは、単なる成績や合格実績では計れない心理的な満足度に関わる話です。
だからこそ私は、塾が戦略を示すのであれば、
「後悔しにくい意思決定の仕方」まで一緒に教える必要があると考えています。
具体的には
・シミュレーションを複数提示すること
・「最悪のケース」「最高のケース」の両方を明示すること
・最終判断はあくまで本人と保護者がするようにすること
あたりが重要になってくるでしょうか。
塾がやるべきは、最適解を押しつけることではなく、
「納得感のある選択の土台」をつくることです。
学習指導がオンライン化され、AI教材も普及し始めた今、
「ただ教える」だけでは塾の存在意義が問われます。
そこで大事になるのは「複雑な事情を整理し、選択肢を共につくる」ことではないでしょうか。
教材選びや学習指導と同じくらい、
「進路の意思決定をどう設計するか」という視点を大事にする必要が出てくると思います。
進路指導は、単なるデータ処理でも感情論でもありません。
生徒さんと一緒に未来をシミュレーションし、
納得のいく選択を一緒に組み立てる「伴走型サービス」です。
最終的に単願制がどうなるかはまだ分かりませんが、
この変化を、「塾の可能性を広げるチャンス」と捉えて対応していきたいですね。
【今回のまとめ】
・単願制廃止が実現すれば、中小塾にとってはチャンスかも
・塾の存在意義が変わってくる可能性も