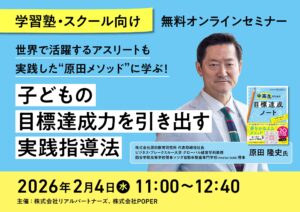学校の成績は、いわゆる「3観点評価」によってなされます。
「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の三つです。
それぞれ、以下のように定義されています。
(1)知識・技能
何を理解しているか、何ができるか
(2)思考力・判断力・表現力等
理解していること・できることをどう使うか
(3)学びに向かう力・人間性等
どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか
つまり通知表などの評価は、これらを総合して判断されるということです。
これをふまえ、先ごろこんなニュースを目にしました。
<指導要領「学びに向かう力」見直しへ 好奇心など追加>
https://www.kyoiku-press.com/post-294749/
短いニュースですが、要は「(3)学びに向かう力・人間性等」について、
教員側の理解や定義があいまいなため、より分かりやすい形で再整理するというものです。
近年の学習指導要領の改革議論において文部科学省が明確に打ち出しているのが、
「学びに向かう力・人間性等」の構造化と重視である。
これは単なる教科知識や思考力の育成を超えて、
学習者の主体性や人間性といった「学びの土台」に光を当てる動きであり、
特に個別指導塾のように生徒さんと深く関わる教育現場では非常に親和性が高い要素です。
言い換えると、個別指導塾の強みが活かしやすい分野だということです。
しかし多くの個別指導塾では、最も成果が分かりやすい
「知識・技能」に焦点が当たりがちです。
定期テスト対策や受験指導がその典型だと思います。
「個別指導塾では」、と言うよりも
生徒さん自身や保護者さんもそれを求めているとも言えるでしょう。
しかし通知表の評価において「学びに向かう力・人間性等」が軽視されることはありません。
いくらテストで良い点を取っても、授業態度や提出物の状況、
主体的な学習姿勢が見えなければ、総合的な評価は下がります。
昔のように、あるいは大学の一般入試のように
「試験の点数さえ良ければ文句は言わせない」とはならないということですね。
むしろ、学校の先生による観察評価が中心となるこの観点こそ、
生徒さんの内面の成長や学習習慣の定着を示す重要な指標となります。
リンクのニュースにもある文科省の特別部会で示した構造案では、
この「学びに向かう力・人間性等」を以下の四つの要素に整理しているようです。
1.初発の思考や行動を起こす力・好奇心
2.学びの主体的な調整
3.他者との対話や協働
4.学びを方向付ける人間性
これらは、テストで点数が取れるかどうか以前の「学ぶ準備力」とも言えます。
もし、現状の塾運営でこうした点を顧みることなく、
「知識・技能(=定期テストや入試の結果)」のみに焦点を当てた指導をしているのであれば、
改善の余地はあるのではないでしょうか。
もちろん、それを分かった上であえて
「当塾は、知識・技能の向上に特化した学習サービスを提供する」と
強い意思を持って割り切るのであれば、それもアリです。
ただ、せっかく個別指導塾をするのであれば、
強みを活かさないともったいないな、とも考えることができますよね。
では、個別指導塾がこの力をどう育み、どう評価に結びつけていけるのでしょうか。
例えば、自習時間などを活用した「自立学習コーチングプログラム」を
試験的に導入してみるのも良いかもしれません。
毎週1回15分程度「リフレクション面談」を行い、生徒さんに
「今週、最も番頑張ったことは?」「どんなときにやる気が出た?出なかった?」
「これをふまえて、来週はどう改善する?」などなど、話をしてみるだけでも違うと思います。
ペア学習(バディ式)を導入し、
生徒さん同士で簡単な課題を互いに説明し合うのも面白いでしょう。
最初は生徒さんも戸惑うでしょうが、回数を重ねていけば
「3.対話力や協働性」が育まれるはずです。
問題があるとしたら、「学びに向かう力・人間性等」は、
テスト結果のように数値化しにくい点でしょうか。
保護者さんからも「そんなことより点数アップの取り組みをして!」と言われるかもしれません。
だからこそ、塾としては観察と記録が重要になります。
行動観察のチェックリストなどを作って
「自ら質問をする頻度」
「宿題の取り組みに対する自己評価の言語化」
「他者の意見へのリアクション(共感・否定・追加意見など)」
を担当講師が週ごとに記録し、面談時に生徒さん本人と共有するイメージです。
さらにこれを保護者さん向けに「成長レポート」として提示することができれば、
学力以外の成長を可視化し、塾の価値を実感してもらえるかもしれません。
個別指導塾は、一人ひとりの状況を深く理解できる点が強みです。
だからこそ、知識の伝達や定着だけでなく、
「どう学ぶか」「なぜ学ぶか」といった根本的な部分を育てる場所にもなれるはず。
私は今後、「成績を上げる塾」から「学びを育てる塾」への変化が
ますます問われるのではないか、と感じています。
単なる演習指導はAIでも代替できる時代にだからこそ、「人が教える意味」の領域――
つまり、学びの動機づけや人間性の支援に本気で取り組むべきではないでしょうか。
【今回のまとめ】
・次期指導要領に向け、学校成績の評価基準が改良される
・「学びに向かう力、人間性等」は、個別指導塾の強みが発揮できる分野