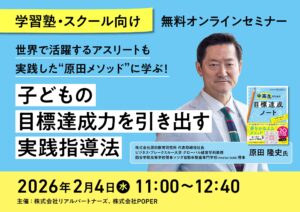教育のデジタル化は、今や完全に一般化してきた感があります。
しかし一方で弊害も見られるようで、
NHKが今後の「デジタル教育との向き合い方」について報じていました。
<進む教育のデジタル化 普及率9割超 効果の一方 想定外の事態も>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250629/k10014847471000.html
教育のデジタル化は、いまや個別指導塾にとっても避けられない潮流ですよね。
AIドリルやオンライン教材を導入して、
効率的に学習したりその履歴を管理したりするサービスは、確かに便利です。
経営的視点で見た保護者さんへの説得力という意味でも魅力的だと言えます。
しかし、こうした流れの中で、記事にもあるような
「アナログ的な身体性の価値」が軽視されているのであれば一考の余地はありそうです。
記事における専門家のコメントでは、
デジタル教材は「負荷をかけない」構造を持つため、
「分かったつもり」になる学習を助長しやすいと指摘されています。
さらに、アナログ的な学びでは
「ゆっくり考える」「回り道をする」「立ち止まる」ことの価値を挙げ、
特に「ノートを手書きするのは全身運動」「定着しやすい」といった
身体性の効用が強調されていました。
これは単なる感覚論や懐古主義によるアナログ信奉ではありません。
神経科学の研究によれば、手書きによる筆記は
キーボード入力よりも脳の活動を広範囲に刺激することが分かっています。
ノートを手書きした学生のほうが、講義内容を自分の言葉に再構成する割合が高く、
後の理解テストの成績も優れているという実験結果が出たそうです。
つまり、身体を使うことで自然に情報を処理しなおす「生成的学習」が起こりやすいのです。
また、教育心理学では「身体性認知」という概念があります。
これは、思考や記憶が脳内処理だけでなく、
身体の動きや感覚を通じて支えられているという考え方です。
例えば手を動かして図形を描く、折り紙を折るといった身体的活動を通じた学習が、
抽象的な概念の理解を深めると考えられています。
こうした知見を個別指導塾に置き換えて考えてみると、
浮かんでくる問いや課題はシンプルなものだと言えるでしょう。
「身体性をどのように商品価値に変換するか」です。
AI教材やオンライン自習アプリは、安価で手軽に演習量を提供できます。
塾に通わずとも、学校や自宅でも実施が可能です。
では、それに対して塾が決して安くはない月謝をいただいて提供するサービスの価値は
どこにあるのでしょうか。
それが「身体を使った記憶定着体験」に潜んでいると考えられます。
例えば、手書きノート指導は塾の大きな武器になるでしょう。
一般的なAIドリルでは解答を選択するだけで終わる問題も、
手書きさせれば、途中式や理由を説明する工程を伴います。
これが認知負荷を適切に高め、理解を深めるというわけです。
さらに、講師がノートをチェックし、間違いや考え方の癖をフィードバックする過程は、
デジタル教材では代替しにくい価値だとも言えます。
また、「実物」系の教材の活用も再評価するべきではないでしょうか。
例えば平面図形を印刷して切り取り、組み立てる。
白地図に自分で国境や地名を書き込む。
こうした作業は、効率重視で考えればデジタル教材よりも明らかに面倒ですが、
この「面倒さ」が「身体を通じた深い処理」となります。
この「負荷の価値」を保護者さんに説明できれば、月謝の正当性も伝えられるでしょう。
「便利」「楽」というデジタル教材の魅力は非常に強力ですが、
それゆえに「楽に学べるが、忘れやすい」という問題も抱えています。
私たち塾経営者は、このデジタルの弱点を正面から説明し、
アナログ指導の価値を商品設計に組み込むべきではないでしょうか。
単にデジタルを否定するのではなく(そもそも否定する必要はない)、
入会面談や広告でも「AI教材との価格差」を正面から比較し、
「だからこそ、身体を使う学びを提供する」と伝えるのもアリだと思います。
もう一歩踏み込むなら、具体的な収益化の方法も考えられますよ。
例えば、アナログ指導特化型の「プレミアムコース」を設計するのも一手です。
通常コースではAIドリル中心で基礎を固め、上位コースでは手書き要約、記述式解答練習、
ノート添削など、身体性を活かした指導を提供する形です。
「書くこと」を重視する大学入試対策とも親和性が高いため、
高等部向けには特に訴求しやすいのではないでしょうか。
一方で、こうしたアナログ指導は講師のスキルに依存しやすい課題もあります。
経営の視点では、属人的なノウハウをマニュアル化し、
講師研修を設計することが不可欠です。
ノート指導のチェックポイント、フィードバックの出し方、
手書き問題の出題例などを共通化すれば、指導品質を安定させられます。
さらに、マーケティング戦略として
「デジタル疲労からのリカバリー」を前面に出すのも有効かもしれません。
保護者さん自身も、テレワークやスマートフォン依存で情報過多の疲れを感じ、
いわゆる「デジタルデトックス」などという言葉も生まれています。
子どもの教育でも「デジタル漬けで大丈夫なのか」という
不安を抱えている層は一定数いるのではないでしょうか。
デジタルに頼る便利さを認めた上で、
「あえて手を動かすことで脳を活性化する塾」というポジショニングは、
こうした不安を解消するメッセージとして共感を得やすくなります。
安価で便利なデジタル教材との価格競争を避けるには、
「身体性」という本質的な学習価値を売る視点が必要です。
ノートを手書きする、実物教材を使う、講師がフィードバックを与えるといったプロセスは、
単なる古臭い慣習ではなく、科学的にも裏付けられた学習の核心のはず。
私たち塾経営者の今後求められるのは、
この身体性の価値を意識的に設計したブランド形成なのかもしれません。
【今回のまとめ】
・デジタルがコモディティ化した今だからこそ、アナログの価値を見直す
・身体性を持った学びを、塾が提供できる価値に