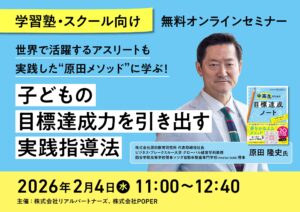OECDが、学校の先生方の労働状況に関する調査結果を公表しました。
<日本の教師の勤務時間が最長 「社会的評価感じる」は国際平均以下 OECD調査
>
https://news.yahoo.co.jp/articles/0759c9099311d17ec32c405967930512c7fe6792
調査によると、日本の先生の労働時間の長さなどが明らかになっていますが、
私が注目したのは、日本の先生方は「教員の社会的評価が低い」と
感じている傾向が強いというデータです。
元データを見てみると、先生方が自らの仕事に対する社会的評価が「高い」と感じるのは、
児童生徒からは54.2%(中学校)、62.0%(小学校)であるのに対し、
保護者からは45.0%(中学校)、49.8%(小学校)と5割切り。
さらに、メディアからの評価に至っては9.2%(中学校)、9.8%(小学校)と、
1割にも満たない結果になっています。
つまり、子どもたちからの評価はそれなりに感じているが、
保護者さんや一般社会(メディア)からは評価されていないと感じているという、
「評価の二重構造」が起こっているということです。
この構造は、個別指導塾の現場にも深く関係する問題だと思います。
「生徒さんから高評価=保護者さんにも評価されている」とはならないのはよくあることです。
生徒さんは辞めたくないと言っているのに、
保護者さんの意向で退塾となるケースも“塾あるある”ですよね。
講師は生徒さんとの距離が近く、日々の指導の中で
「先生、わかりやすい!」といったポジティブな反応を得る機会が多くありますが、
多くの保護者さんは「成果」でしか判断しにくいからです。
教育心理学では、同じ教育行為でも、
受け手によって評価の基準が異なることが知られています。
例えば、生徒さんにとっての塾の価値は「楽しい・分かりやすい・励ましてくれる」といった
感情的・体験的な評価軸に重きが置かれます。
一方で、保護者さんにとって塾の価値は「成績が上がる」「安心して任せられる」といった
成果・信頼性の評価軸が中心です。
保護者は基本的に、塾に対し、費用に見合うだけの学力向上や進路実績を期待しています。
もしその期待に対して成果が見えなければ、講師がどれだけ子どもに好かれていようとも、
「あの塾は効果がない」「なんとなく不安」といった否定的な評価につながりがちです。
つまり、生徒さんとの関係構築だけで満足してしまうと、
保護者さんとの評価軸にズレが生じ、
退塾などの経営上のリスクに繋がる可能性があるわけですね。
ただ、ここで注意したいのは、保護者さんの評価が低くなる背景には、
「成果が出ていない」のではなく、「成果が伝わっていない」と見るべき部分も
あるのではないかということです。
学校でも、先生方の多くが子どもとの関係にやりがいを感じつつも、
メディアや保護者さんに十分に発信できず、社会的評価が低迷して(いると感じて)います。
塾も同様に、内部では「丁寧な指導」「小さな成長支援」が
積み重ねられているにもかかわらず、
それを外部に見える形で発信できていないケースが少なくありません。
教育の成果は短期的に数値化しにくい面があり、
テストの点数や模試の偏差値だけでは測れない部分も多いのはみなさんもご存じのとおり。
しかし、保護者さんはそうした「見えないもの」に対して不安を感じやすいものです。
社会心理学の「認知的不協和」理論に照らしても、
人は支払ったコストと実感する成果が一致しないと、
違和感や不満を覚えやすくなることが分かっています。
つまり、支払った月謝や送迎の手間などと、
支出や労力と目に見える成果が釣り合わないとき、
保護者さんの心には「本当にこの塾でいいのか?」という疑念が生まれやすくなるのです。
そこで鍵となるのは、やはり保護者さんとの「評価軸の擦り合わせ」でしょう。
生徒さんとの関係性をベースにしながらも、
保護者さんに対しては別のアプローチを設計する必要があります。
例えば、定期的な面談や月次レポートで、
「授業内容」「小さな成長」「努力のプロセス」を丁寧に伝えることは有効です。
単にテストの点数を報告するのではなく、
「以前は宿題を忘れがちだった生徒さんが、今では毎回期限を守るようになった」といった
小さくても具体的な変化を共有することで、我が子の成長を実感しやすくなります。
講師は生徒さんと接するのがメインですが、
教室長や塾長は保護者さんとの接点を意識的に持ち、
塾の方針や教育理念を伝え続けることが大事でしょう。
講師個人の指導力への評価にとどまらず、
組織としての信頼感を醸成することが大事だと思います。
今回の調査結果に見られるような「評価の二重構造」は、
まずそのような二重構造が存在することを自覚するのが第一です。
生徒さんからの評価が高くても保護者さんからは低い、
あるいはその逆もあるという前提に立った上で、塾運営をしていく必要があります。
しかし逆に言えば、この構造を正しく理解し、
保護者さんとの評価軸の違いを戦略的に埋めていくことができれば、
塾の信頼性と継続率を大きく高めることができるはずです。
ルーブリック評価を用いて、
勉強に向かう姿勢などテストの点数以外の評価軸をいくつか設け、
到達度という視点でフィードバックするのもよいかもしれません。
生徒さんと保護者さんは、それぞれ異なるレンズで塾を見ています。
それをふまえて、自塾が生徒さんの何を育てようとしているのか、
入塾時や面談時などにしっかり共有していきましょう。
【今回のまとめ】
・塾に対する、生徒さんと保護者さんの評価は異なるもの
・子どもの成長を実感できる、直接的学力以外の評価軸を設定し、共有する