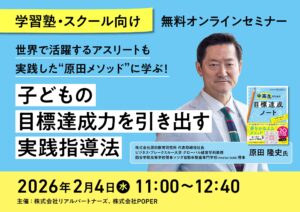岡山県内から女子校が消滅するという、なかなか衝撃的なニュースを目にしました。
<清心中学・女子高が2027年度に共学化 岡山県内で女子中高ゼロに>
https://www.asahi.com/articles/ASTB83QW2TB8PPZB005M.html
岡山市の清心中学校・清心女子高校が2027年度からの共学化を決定したことで、
同県内の女子校はゼロになる見込みなのだそう。
背景にあるのは、少子化に起因する市場規模の縮小です。
志願者数の減少は避けられず、経営的にも共学化は合理的な判断なのでしょう。
しかし、このニュースを私教育業界、特に中小規模の個別指導塾経営の視点から見ると、
また違った考え方もできるかもしれません。
縮小市場における「熱狂的少数派」を意識したマーケティング戦略です。
女子校がなくなるということは、「女子校に通いたい」というニーズが
完全に消えることと同義ではありません。
むしろ、女子校志向の家庭は一定数、確実に存在しています。
女子校が持つ独自の教育環境や文化、価値観を重視してきた層です。
ネット販売などでよく用いられる「ロングテール理論」によれば、
売上を人気商品に頼りきるのではなく、ニッチな(あまり売れない)商品の販売を積み重ねて、
全体の売上を担保していく戦略が提唱されています。
塾市場でも同様で、「多数派向けの塾」が飽和する一方で、
「少数派向け」の塾が確実に支持を集める土壌はあるのではないでしょうか。
女子校志向のような少数派ニーズに丁寧に応えることで、
顧客は単なる「利用者」から「ファン」へと変わります。
マーケティング分野では、こうした熱狂的少数派を「True Fans(真のファン)」と呼び、
1000人の熱狂的ファンがいれば、持続可能な経営ができるという考え方があるそうです。
このような「少数派×熱狂的ファン」戦略は、教育以外の分野でも成功事例が豊富です。
例えばアパレル業界では、大量生産・大量販売を志向する大手ブランドの一方で、
特定の価値観に共感するコアなファン層に支えられたD2Cブランドが台頭しています。
環境配慮型やジェンダーレスなど、特定の文脈に強く共鳴する少数派に的を絞ることで、
ブランドの世界観が深まり、ファンコミュニティが形成されるのです。
塾業界でも、教科特化型の塾をはじめ、この時代にあえてスパルタ方針を貫く塾や、
「総合型選抜専門塾」「○○中学専門塾」、「○○高校志望者専門塾」
「探究専門塾」「発達・学習障害専門塾」「不登校者専門塾」など、
尖った個性で支持を集めている塾はたくさんあります。
女子校志向など、特定の教育理念に共感する少数派に焦点を当てることで、
小さくても強いブランドを作るチャンスはあるということです。
多くの塾経営者が、市場縮小を前にして
「とにかく間口を広げ、多数派に合わせる」方向に舵を切ります。
しかし、それでは大手塾さんと真正面から競合する構図になってしまい、
資本力・知名度で劣る中小塾は不利です。
むしろ、縮小市場において重要なのは、
「最大公約数」を狙うのではなく、「最小公倍数」を見つけることではないでしょうか。
つまり、すべての人にとって“まあまあ”な塾になるのではなく、
ある特定の人にとってはまったく見向きもされなくても、
また別の層から見れば「かけがえのない塾」になるということです。
そのためには、ターゲットを明確にし、
その層の価値観や期待に深く寄り添う必要があります。
女子校がなくなるというニュースは、
「女子校志向は少数派だからやめよう」という話ではありません。
むしろ、「少数派であっても、その声に丁寧に応えれば、強固な支持を得られる」という
ヒントではないかと思います。
「女子校がなくなる=女子校ニーズが完全に消える」ではないと申しましたが、
数が少なくなればなるほど、消費者(ファン)の中でその価値が高まることがあります。
いわゆる「希少性バイアス」です。
人は希少なものほど価値を高く感じ、強い動機づけを受ける傾向があり、
例えば、同じ商品でも「残りわずか」と表示された途端に購買意欲が高まったり、
期間限定の商品に人が殺到したりするのはこの原理によるものです。
この解釈で言えば、岡山県から女子校がなくなることで、
「女子校で学ぶ」という選択肢は(岡山県では)一気にレアなものになります。
すると、女子校ファンは「希少な教育環境を手に入れたい」という意識が強まり、
女子校がある近隣他県への進学なども視野に入れるかもしれません。
この心理を理解し、塾経営にうまく取り入れることができれば、
市場が縮小している中でも逆に存在感を高めることが可能なはずです。
少子化は今後も進み、市場全体は縮小していきます。
しかし、それはすべての需要が一様に消えるという意味ではありません。
女子校の例が示すように、少数派ニーズは確実に存在し、
そこに寄り添えば強い共感と支持を得ることができます。
塾経営においても、「数が減った」からといって単に撤退や多数派迎合をするのではなく、
「熱狂的少数派」に目を向け、その声に応える戦略は持っておいて損はないと思います。
市場全体が均質化しつつある今こそ、“オンリーワンの塾”が輝くチャンスかも!?
【今回のまとめ】
・女子校の消滅=ニーズがゼロとは限らない
・ロングテールや希少性バイアスを意識して、尖った塾に