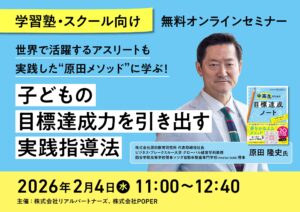先日、全国小・中学校作文コンクールの受賞作を読んでみました。
みんな本当に素晴らしい作文で、私には到底書くことができない表現力です。
さらに年度を遡って、過去の受賞作を読んでみた際、すごく惹かれた作文がありました。
【自閉症を持つ私から見た日常(大阪青凌中学校3年藤田壮眞)】
https://jigyou.yomiuri.co.jp/sakubun/prize/000337.html
自閉症の藤田さんが見える世界を作文で表現してくれています。
私には想像もできない考えや思いがあったことを認識させてもらいました。
作文にして具体的な内容を書いてもらうことで、
当事者が何に悩んでいる・悲しんでいる・辛い思いをしているのか
知ることができたとも言えます。
特に、最後のまとめの部分が強く印象に残りました。
原文ママ(後半部分)
=====)
自閉症の子供が産まれて、悲しむ家族もいるだろう。でも私達(たち)は学ぶし、成長する。
人の気持ちが分かりにくいけれど、人が嫌いではない。
小学校では床で寝転んでいたが、今は椅子に座り、必死に勉強している。
私達にはみんなと同じだけの未来があり、期待を持っている。
私が間違った時は、あきらめないで教えて欲しい。
私もこの困難な世界に向き合い、痛みを知っているぶんだけ、弱さを持っているぶんだけ、
他の誰かに優しくなれる大人になりたいと考えている。
=====
口に出したり表現できたりていなくても、いろいろな思いを感じていて、
人の気持ちが分かりにくくてもどうにかしようという思いを
強くもっておられることを改めて感じます。
「私が間違った時は、あきらめないで教えて欲しい」というメッセージは、
個別指導塾に携わる人間として、心に留めておかないといけない部分ではないでしょうか。
発達障害を伴わない、身体的・知的・社会的な発達が平均的な範囲に収まっている状態を
「定型発達」というそうで、発達障害の対義語として使われると妻から教えてもらいました。
定型発達に該当する人たちからすると、作文の内容も
なかなか実感値としてイメージしにくいことや、正直理解できない内容もあるかもしれません。
しかし今の日本(だけではないと思いますが)では、
大多数である定型発達に合わせた社会構造やシステムになっていると思います。
学校などは特にそうではないでしょうか。
例えば中学校なら、1985年以降変わらない
1クラス40人の集団授業(2026年度より35人になる予定)をはじめ、
校外学習や体育大会など、集団でともに生活をしていく形です。
もちろん学校は社会性を学ぶ場でもありますので、一概にそれを否定はできませんが、
どうしてもマイノリティーに対する配慮や枠組みなどが足りていないのと思うのです。
作文にもあったように、授業中、クラスメイトの動きやャーペンの音、エアコンの音などで、
先生の声が聞きたくても聞こえない特性を持つ生徒さんには、
一般的な学校の集団授業は苦痛でしかありません。
子どもの特性や個性を加味して個別対応しようにも、
学校の先生にだって物理的な限界があるでしょう。
であれば、個別指導塾こそ、生徒さんの特性を把握した上で環境を変え、
いきいきできる形を作る存在になり得ると思います。
むしろ、そういったことをするために
個別指導塾が存在すると言っても過言ではないかもしれません。
実際に、生徒さんにもさまざまな性格やタイプがあります。
パッと見、おとなしめで物静か、こちらからの働きかけに対し
反応が薄い生徒さんもいるかもしれません。
何度も同じ問題を間違えたり、学んだことをすぐに忘れたりする生徒さんもいるでしょう。
そういう子どもたちに対して「やる気がないのかな」と思ってしまうケースもあるはずです。
もしそういった生徒さんがあなたの塾にいるのであれば、
「反応が薄いのは性格で、本当は理解できて満足している」、
「何度も間違えるのはやる気がないわけではなく、必死で頑張ろうとしている」、
「すぐに忘れるのは特性で、本人も覚えようとしている」
といった視点持つことが大事だと思います。
それによって生徒さんへのアプローチも変わってきますし、
生徒さんも「この先生は自分のことをとても理解してくれている」という思いになり、
信頼関係を構築しやすくなるはずです。
定型発達よりの個別指導塾関係者が、
自分の感覚や価値観だけで生徒さんに接するのはとても危険だと思います。
生徒さんの本当の心の叫びをキャッチできないおそれがあることを
肝に銘じておきたいところです。
ちなみに、知り合いにシニア向けのパソコン教室を経営されている方がいるのですが、
「私たちは同じことを100回聞かれても、笑顔でお答えします」
というキャッチコピーを掲げています。
本当に上手いキャッチコピーだなと思いますし、安心感しかありませんよね。
私たちはつい、広告上でも「面倒見が良い」とか「地域密着」とか、
抽象的な言葉をキャッチフレーズに掲げがちです。
しかしこのコピーは「あなたのことを分かっているよ」「寄り添うよ」という姿勢を、
具体的な行動例として示しています。
塾に通う生徒さんにも通じるものがあり、
これぐらいのことを伝えておいたほうが生徒さんも安心して通塾できるのではないでしょうか。
あとは、こうした考えを塾長だけでなく、
講師(社員・アルバイト)も実践できるように研修をしておく必要があります。
塾長だけ粘り強く何度も丁寧に接しても、
学生アルバイトが「なんでこんなこともできないのか」んもすぐできひんの?」
なんて言ってしまえば、関係性は一瞬で終わりです。
「実は心の中ではこんなこと考えているのかも」、
「本人が頑張ろうという姿勢がある限り、こちらも応援し続けよう」など、
生徒さん一人ひとりが特性や個性を持って、
しっかりと学ぼうという気持ちを持っていると考えれば、私たちの引き出しも増えていくはず。
違った切り口での指導法を考えるきっかけにもなるでしょう。
通塾している時点で、個人差はあれど
「できるようになりたい」「成績アップしたい」と思っているはずなのです。
やる気がないよう見える生徒さんほど、
こちら側が工夫し、歩み寄って伴走してきたいですね。
とにかく、いろいろな個性や特性をもった生徒さんがいて、
その対応を個別で行うから個別指導塾なのだという原理原則を忘れずに、
その思いを全スタッフが共有して一貫性を持たせることが欠かせません。
私たちも知らないことがたくさんあり、まだまだ学ぶ身であることを常に意識し、
生徒さんに対しても自身の感覚だけで接することのないようにしてみませんか?
私も日々勉強です!
【今回のまとめ】
・個別指導塾だからこそ、特性や個性に合わせた対応ができる
・やる気がないように見える生徒さんほど、その個性や心理に寄り添ったサポートを