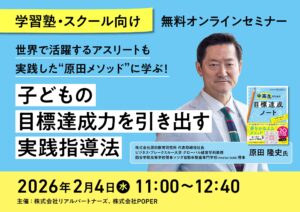先ごろ、意外(?)な調査結果を目にしました。
20代会社員の「忘年会参加意向が高い」というのです。
<Job総研『2025年 忘年会意識調査』を実施しました>
https://jobsoken.jp/info/20251117/
近年、若者は「会社の飲み会が嫌い」「飲みニケーションは不要」という
価値観が一般常識として語られてきましたよね。
しかし今回のデータを見ると、むしろ20代のほうが職場忘年会に積極的で、
30代、40代と年代が上がるにつれて参加意欲が下がっていることが分かります。
正直、私はかなり驚いたのですが、みなさんはいかがですか!?
この原因について、専門家からは、
コロナ禍によるコミュニケーション不足の反動ではないかという指摘が出ているようです。
そこで今回は、この意外なデータから、
私たち塾経営者が何を受け取るべきか考えてみましょう。
パッと思いつくのは、忘年会を含め、講師たちとのコミュニケーションイベント開催に
もっと積極的になってもよいかもしれない、ということでしょうか。
ただ、より大事なのは「最近の若者は○○だ」というステレオタイプの印象がいかに脆く、
そして現実を見誤らせる危険な枠組みであるか、ということだと思います。
例えば塾の現場では、「最近の子は忍耐力がない」「親が過保護になっている」
「スマホ世代は集中できない」といった「世代論」が語れることって多いですよね。
もちろん、時代背景によって行動傾向が変わる側面はあるでしょう。
しかし実は、こうした世代論の多くは、
データで検証すると「意外とそうでもない」ことが判明するのだそうです。
例えばアメリカの心理学会がまとめた研究では、
「Z世代は上司を尊敬しない」「ミレニアル世代は怠惰」という一般論は
実証的な裏付けがほとんどなく、むしろ個人差のほうが大きいことが示されています。
行動科学的にも、人の行動には、年齢よりも
「環境」「経験」「周囲の期待」といった要素ほうが強く影響するというのが定説です。
だとすると、「最近の子は集中できない」などと決めつけて指導方針を立てることは、
的外れな施策を生み、塾が持つポテンシャルや可能性を狭めてしまう危険性があります。
では、なぜ今回の調査で、若者の行動は世代論と異なる方向に動いたのでしょうか。
仮に、「コロナ禍による経験の不足」が要因だとすると、
若者は人と直接つながる経験が長らく奪われてきたため、
その反動で「リアルな場」に価値を見出すようになった可能性があります。
つまり、私たちはついそれを「世代の価値観」を切り口として捉えがちですが、
実はそうではなく、環境変化が行動を変えただけということです。
塾経営においても、こうした「思い込み」の要素が強い“常識”は少なくありません。
例えば、下記のような一般論は、本当にそうだと言えるのでしょうか。
・内向的な子は、集団より個別指導のほうが向いている
・競争心が強い子は集団指導に向いている
・塾に来て長時間自習をしている=頑張っている
・スマホは学力を下げる
もちろん「間違っている」とまでは断言できませんが、こうした言説は、
誰かが「なんとなくそう感じる」ところから始まり、
それが現場の暗黙ルールになってしまうケースが多々あります。
今回の忘年会データも同じで、「若者は会社の飲み会が嫌い」という固定観念があるため、
逆のデータが出た時に(私を含め)驚きをもって受け止められたわけです。
つまり世代論とは、現実よりも先に固定観念が勝ってしまう現象なのかもしれません。
では、塾はどのように運営を見直すべきでしょうか。
1.生徒さんの行動データを定期的に可視化する
「今年の中1はなんとなく集中力に欠ける」で片づけるのではなく、
自習室の滞在時間、宿題提出率など、簡単に取れるログでも傾向が見えてきますので、
具体的なデータに基づく分析で対策を考えてはどうでしょう。
2.保護者アンケートを仮説検証の装置として使う
「普通、保護者さんはこうしたもの(成果やサービス内容)を望んでいるだろう」ではなく、
アンケートなどでストレートに要望を聞いてみるのも一つの手です。
意外なギャップに気づくことができるかもしれません。
3.スタッフ間で「思い込みの棚卸し」を行う
みんなで「(あまり深く考えず)こういうものだと思っている」という常識や一般論を
出し合ってみるものよいかもしれません。
データドリブンな塾運営は保護者さんからの信頼度を大きく高めます。
「“なんとなく”で指導方針を決めない」「データをもとに改善する」……
こうした姿勢は、納得度や安心感が違うはずです。
そしてその第一歩が、まさに今回の忘年会データが教えてくれたような
世代論の罠から抜け出すことなのかもしれません。
時代が大きく変わったわけでも、若者の価値観が一斉に反転したわけでもありません。
変わったのは、私たちの側の「理解の仕方」。
「最近の子は〜」「この年代の親は〜」、そうした固定観念を基準に施策を考えるのではなく、
思い込みから自由になる改革を進めていきましょう!
【今回のまとめ】
・世代論は意外と当てにならない
・先入観で考えず、できるだけデータなどの裏付けを取って施策を作ろう