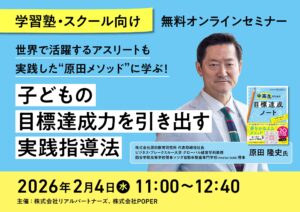近年、保護者さんの価値観(教育観・子育て間)が大きく変化してきています。
そんな中で目にしたのがこちらの調査結果です。
<お出かけで学校を休ませてもいい? 8割の保護者が賛成と回答した理由>
https://research.iko-yo.net/solutions/research/12219.html
この調査によれば、約8割の保護者が
「お出かけや旅行のために子どもを学校・園を休ませる」ことに
肯定的な考えを示しているそうです。
保護者さんたちは「家族の時間を大切にしたい」「学びは学校の中だけではない」という
価値観を持って行動しているわけです。
不登校などの問題も含め、かつてのような
「学校を休む=悪」という前提は揺らぎつつあります。
こうした「家族との時間」を重視する保護者さんに、塾はどう向き合えばよいのでしょう?
その一つのカギとなるのが、単なる教務力や合格実績だけではない
「共感ベースのコミュニケーション力」ではないかと思います。
心理学者のカール・ロジャーズ(米)は、良好な対人関係に必要な条件として
「共感的理解(empathic understanding)」の概念を挙げています。
これは、相手の視点に立って感情や価値観を理解しようとする姿勢で、
教育の現場でも極めて重要な発想です。
特に近年の保護者世代は、「自分たちの価値観に寄り添ってくれる教育機関」を
求める傾向が強まっています。
実際、上述のアンケートでも学校を休ませる理由について
「平日の混雑を避けて家族旅行をしたい」「子どもの新しい体験を重視したい」など、
合理性と情緒性(感情)が共存した意見が多く見られました。
つまり保護者さんは、ただの気まぐれやワガママで学校を休ませているのではなく、
「この子にとって何が本当に価値ある経験なのか?」を真剣に考えているのだと言えます。
これを塾に置き換えて考えてみましょう。
例えば「旅行に行くから塾を休ませたい(=塾よりもレジャーを優先したい)」という
希望があった場合、それをどう受け止めるかです。
まず「休むなんて絶対ダメ」「学力が落ちる」と一方的に一刀両断しまうようでは、
たとえ指導力があっても信頼を得にくくなります。
一方で、「なるほど、それも大切な経験ですね」「その体験を学びに活かしましょう」
と受け止めることができれば、塾は「家族の味方」として支持されやすくなるでしょう。
もちろん、応じる・応じないに正解はないと思います。
基本的には塾の理念や方針に従って意思決定すれば良いと思いますが、
もし「休みたい」という希望に柔軟な姿勢で臨みたいのであれば、
実務としてどのように「共感ベースのコミュニケーション力」を実践すればよいでしょうか。
主には3点考えられます。
- 「価値観の共有」を意識したヒアリング
面談の際には志望校や学力だけでなく、
「ご家庭で大切にしていること」「お子さんにどう育ってほしいと考えていますか?」といった
価値観ベースの質問を加えてみるのはいかがでしょう。
これにより保護者さんも「この塾は数字だけでなく、子どもの人生を一緒に考えてくれる」と
感じてくださると思います。
- 欠席や休みを否定せず、活かす視点で受け止める
「旅行で休む」と言われても、それを咎めるのでも、
「どうぞ休んでください」と淡泊に対応するのでもなく、
「その体験を学びに活かす機会」として扱う姿勢が重要です。
例えば「旅行先で見たものをテーマに作文を書いてみてはどうですか?」、
「日記をつけて、語彙力のトレーニングになりますよ」
「自由研究や探究学習の素材探しになるかもしれませんね」などと提案できれば、
塾の価値は大きく高まるはずです。
- 塾のメッセージにも「共感」を組み込む
HPやパンフレットの文面にも、「家族の時間を大切にしたいご家庭の学びを応援します」
「学びは日常の中にある」といった言葉を盛り込む(意思表示をする)ことで、
保護者さんに安心感と共感を与えることができます。
かつては成績向上や志望校合格が塾業界の“成果”や“価値”主流でしたが、
今は「家庭の価値観に寄り添ってくれるかどうか」という文化も生まれています。
特に中小規模の個別指導塾においては、経営者や講師の顔が見える、
個別対応が柔軟にできるといった点が強みです。
その強みを最大限に活かすには、「共感」という視点が欠かせません。
学校でも、学びを目的に平日に学校を休むことを認める(欠席扱いにならない)
「ラーケーション」を取り入れる自治体の動きが目立ち始めました。
<ラーケーション>
https://www.travelvoice.jp/20240425-155511
塾も、子どもが「平日に家族旅行に行くこと」を「学びの逸脱」と捉えるのではなく、
「人生経験の一部」として尊重できるようになることが求められているのかもしれません。
ただ、勘違いして欲しくないのは、休みを受容することと、
単に保護者さんにおもねることやへつらうことは違うという点です。
どのような対応をするにせよ、何が生徒さんにとって利益になるのか、
その意識を忘れないように判断することが大事ではないでしょうか。
【今回のまとめ】
・学校や塾を「休む=悪」の時代ではない
・子どもの利益を最優先しながら「共感的理解」を