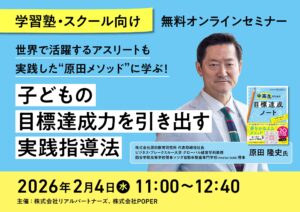恒例の「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)の結果が公表されましたね。
<全国学力調査の結果を公表 都道府県別に「大きな差はない」>
https://www.asahi.com/articles/AST9Z2PLPT9ZUTIL00BM.html
同じく恒例となっているのが、結果が毎年報じられるたびに、
「どの県が上位か」「正答率が何%か」といった数字ばかりが大きく取り上げられ、
独り歩きしてしまうことへの是非です。
みなさんもご存じのように、全国学力テストは
「全国学力・学習状況調査」が正式名称であり、あくまで「調査」です。
テストをすることで、現状の教育の課題を見出し、
改善に役立てることが目的であるはずなのに、順位ばかりが着目され、
県によっては対策テストまで行っているという本末転倒ぶり。
学校も、私たち学習塾も、そして生徒さんや保護者さんも、
調査の趣旨を正しく認識する必要があるでしょう。
もっと言えば「テスト」とは何のためにあるのかという前提から見直すことが大事です。
具体的には、模試や定期テストでの点数が、まるで学びのゴールであるかのように扱われ、誰もがその先入観にとらわれてしまっていることに、強い危機感を覚えます。
もちろん、ある意味でのゴールや目的に位置付けられるテストがあるのも事実でしょう。
入試などはまさにその典型です。
学校の定期テストも、それが評定に影響することを考えれば、
目的化してしまう部分もあるのは仕方ありません。
しかし本来、日常的な小テストや確認テスト、模試などは学びの通過点にすぎません。
そこで測られる点数はあくまで現在地点を知るための「指標」であり、
教育の目的そのものではないはずです。
塾がこのことを忘れ、点数をゴールとして扱ってしまうと、
学習指導の質が短期的な成果偏重になり、
長期的な学びの力を育てることが難しくなってしまいます。
先日読んだ教育系のコラムで、「なるほど」と思ったことがあるので引用します。
「評価」と「評定」を一緒にしてはいけないという論です。
そのコラムによると、評価とは、あくまで現状を分析して
よりよい学びをもたらすためのフィードバックやコミュニケーション、
評定とは、ある一定の時期における学習到達度を数値化した客観指標のことだとありました。
確かにそうですね。
目先のテストの点数は本来「評価」に用いるべきものなのに、
「評定」と混同している部分があるのだと思います。
だから、入試ではない、日常的なテストの点数まで「目的化」してしまうのではないでしょうか。
塾を経営していると、保護者さんから「次の模試で何点くらい取れるでしょうか」
「偏差値をどれくらい上げられますか」と尋ねられることが多くなりがちです。
もちろん成績向上を期待するのは当然のことですが、
そのやりとりが「点数を上げること」=「学びの目的」という
誤解を強めてしまっている可能性は否定できないでしょう。
生徒さん自身も同様です。
「テストの点を上げること」だけを目的にすると、勉強のプロセスに意味を見いだせなくなり、
努力を「成果が出るかどうか」でしか評価できなくなります。
学びは(テストでよい点を取るための)テクニック化し、
「これを学んで何の意味があるのか」などという価値観が定着してしまいます。
このような「外発的動機づけ」では、長期的なモチベーションは維持できません。
高校や大学に入ってから起こる燃え尽き症候群も、その影響があるのでしょうね。
教育は短距離走ではなく、長距離走です。
短期間で得られる点数は、あくまで途中経過のラップタイムにすぎません。
マラソンを走る人が「5キロの通過タイム」だけで走り方を決めてしまったら、
本来のゴールまで走り抜くことは難しくなるでしょう。
同様に、テスト結果をゴールと見なすことは、
学習者が「長い目で学びを積み上げる」姿勢を持つ妨げになります。
では、塾はどうすれば「テスト=ゴール」という思い込みから
生徒さんや保護者さんを解放できるのでしょうか。
大切なのは、テストを「学習の現在地点を知るためのツール」として
正しく位置づけ直すことです。
例えば模試の結果を返却するときに、「偏差値が○○になりました」で終えるのではなく、
「この問題では本文の要点をまとめきれていない」「この計算は途中の理解が弱い」といった
学習プロセスに焦点を当ててフィードバックすることが有効だと思います。
誤答から学びを抽出し、「次にどんな学びを積み上げるべきか」を具体的に提示することで、
テストをゴールではなく通過点として捉え直すことができるはずです。
また、保護者面談でも「点数の上昇」だけでなく
「家庭学習の習慣が定着してきた」「自分から質問するようになった」といった
非数値的な成長を共有することも重要だと思います。
塾がこうした「見えにくい成長」を保護者さんと共有できれば、
点数偏重から一歩抜け出すことがでるのではないでしょうか。
もう一つの鍵は、やはり生徒さん自身の学習観を変えることでしょう。
子どもたちはどうしても「テストでいい点を取れば努力が報われた」と考えがちです。
しかし「よい点が取れなくても、努力した過程に価値がある」と気づかせる指導こそが、
長期的な学習者としての姿勢を育てます。
たとえば「振り返りシート」を使って、テストごとに
「どんな準備をしたか」「どの部分で時間が足りなかったか」「次は何を意識したいか」を
客観認識できる仕組みを作ることなどは効果的です。
これは教育心理学でいう「メタ認知能力」を育む取り組みであり、
自分の学びを自分でコントロールできる子どもを育てることが分かっています。
全国学力調査をめぐる議論は、
教育が「点数のための競争」に傾きやすい現実を映し出しています。
これは決して学校だけの問題ではありません。
むしろ学習塾は、テストの成績を成果指標に掲げやすいぶん、
その先入観を強めてしまう危険があります。
だからこそ塾は、「テストはゴールではなく通過点である」という視点を
明確に打ち出すことが大事ではないでしょうか。
生徒さんには「努力の過程に意味がある」と伝え、
保護者さんには「点数以外の成長」を示し、
塾自身も「誤答や習慣を分析し改善する文化」を持つ。
そうした取り組みを積み重ねてこそ、短期的な成果にとらわれない、
長期的に自立した学習者を育てることができるはずです。
伴走者として、子どもたちが「テストの先」を見据えられるように導いていきたいですね。
【今回のまとめ】
・テストの結果自体を目的化しない
・評価と評定を混同しない学習サポートを