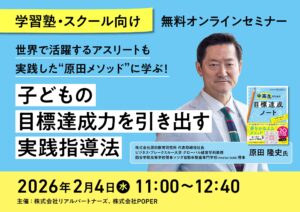先ごろ文科省が公表した「21世紀出生児縦断調査」の結果が非常に興味深かったです。
<第23 回 21 世紀出生児縦断調査(平成13 年出生児)の結果について公表します>
https://www.mext.go.jp/content/20251023-mxt_chousa01-000045531_01.pdf
同調査は、平成13年(2001年=21世紀の始まり)に生まれた子どもたちを追跡調査し、
その意識の変遷などを他の世代とも比較しながら、
教育施策に反映していくために実施しているものです。
特に私が注目したのは、「現在の仕事に、学校で学んだことが生きている」と
感じるかどうかを尋ねた質問で、全体では52%ほどが肯定的な意見だったのに対し、
学歴によってばらつきが大きかったことです。
高専・専門学校卒は7割前後が「生きている」と答えた一方、
大卒では5割強、高卒では3割強という結果でした。
高専や専門学校は、仕事に直結する技術や知識を学ぶ場ですから、
まあ妥当な数字だと言えるのかもしれません。
気になるのは大卒者や高卒者の数値です。
例えば大卒者の5割が「仕事に生きている」と感じているということは、
逆に言えば残りの5割は「生きていない」と思っているわけですよね。
一般的には、大学など「高度な教育」を受けた人ほど、
学びを仕事に生かしているのだろうというイメージがありますが、
「大学まで出ているのに、学びを仕事に生かせていない人」がこれだけいるということです。
なぜ、高専卒や専門学校卒とこんな差が生まれてしまうのでしょう。
よく「学校で学んだことなんて社会では役に立たない」と、
学校教育を揶揄する意見も耳にしますが、私は、この数字を
「学校で学ぶ内容の有用性」に回収してしまうのは危険だと感じています。
むしろ問題なのは、「学んだことを自分の仕事に結びつける転換力」が
育っていないことではないでしょうか。
つまり、学びが役に立たない」のではなく、
「役立て方を知らない」「役立てようという応用意識がない」と
考えたほうがよいのではないかということです。
あえてもっと厳しく言えば、すぐに使える正解のようなものや、
お膳立てされた学びの成果を口を開けて待っているだけで、それを与えられないから
「学校の学びは役に立たない」などと責任転嫁しているようにさえ見えます。
教育学や心理学では、学んだ知識を新しい場面へ応用する力を「転移」と呼びます。
学習、特に高校までに得る学びの最大の目的は、この「転移」の種を蒔くことです。
しかし、多くの子どもたちは、学校で学んだ知識を
「テストで使うもの」としか理解できていない現実があります。
この状態では、社会に出たときに「仕事に使える」という感覚を持ちようがないですよね。
反対に、高専や専門学校の学生は、座学と実技を往復する機会が多いため、
自然と「抽象→具体→抽象」の循環を経験します。
学んだことの意味を自分で構築し直す経験の多さが、
「仕事に生きている」という感覚につながるのです。
つまり、この調査結果における学歴による差は「(勉強の)優秀さ」の差ではなく、
意味づけの経験量の差と見たほうが正確なのではないでしょうか。
その点で個別指導塾は、実は「転換力を育てる」教育に極めて適した業態だと感じます。
(1)一人ひとりに合わせて説明の抽象度を調整できる
(2)「なぜその考え方をするのか」を言語化させられる
(3)思考のプロセスを丁寧に対話しながら作り直せる
といった特徴を持っているからです。
学校では時間の制約があり、教師が数十人もの生徒全員の
「意味づけ」まで面倒を見ることは難しいでしょう。
しかし個別指導塾なら、その子の理解度や興味関心に合わせて、
学びと現実世界の橋をかけることができます。
例えばこんな質問を投げかけるだけでも、転換力は鍛えられると思います。
「今日の解法って、日常のどんな場面で役立ちそう?」
「この国語の読解力って、将来どんな仕事で強みになると思う?」
「今回のミスは、どうしたら次回や別の科目にも応用できるかな?」
正解は必要ありません。
大切なのは、「関連づけようとする思考習慣」を持たせることです。
実は、最近のキャリア研究でも、早期離職の大きな要因の一つとして
「学生時代に自分の学びを職業と結びつけられないまま就職した」ことが指摘されています。
つまり、転換力が弱いまま社会に出ると、
職業選択にも入職後の適応にも苦戦しやすいのです。
では、そうした課題において塾は何を担えるのでしょうか。
私は、「学習内容を教える場」から一歩進んで、
「子どもが学びの意味を自分で編集できるようにする場」へと
アップデートすることだと思います。
しかし、何も大げさな改革である必要はありません。
例えば授業の最後に30秒だけもいいので、
「今日の学びを、一言でまとめるとしたら?」
「今日の気づきを、他の科目に応用するとしたら?」
「今日得たスキルを、未来の自分はどう使うだろう?」
というリフレクションを続けるだけでも、
生徒さんは自然と「意味を探す脳の使い方」を身につけていけるはずです。
学びが仕事に生きないのは、学びが無価値だからではありません。
「つなげ方」を教わらないまま大人になってしまっているだけです。
だからこそ、個別指導塾にはまだまだできることがあります。
子どもたちに知識を渡すだけでなく、
その知識を未来につなげる回路(転換力)を育てることを意識してみませんか。
【今回のまとめ】
・若者の半数が「学校での学びが仕事に生きていない」と思っている
・学びが無価値なのではなく、転換するスキルが足りていないだけ。塾でそれを育てよう