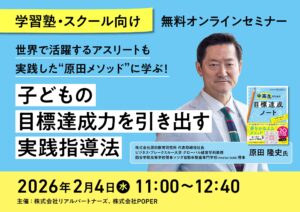大手予備校・河合塾さんで、
講師が授業中にストライキを決行したというニュースが報じられました。
<河合塾講師が異例のストライキ 物理の授業で15分間、授業1分35円の賃上げ求め>
https://www.sankei.com/article/20250521-R2WW52HHOBLUJDWIONU7B5XDXI/
この動きは、単に労働条件の問題にとどまらず、
教育業界全体が今後直面する「講師の声をどう扱うか」という
課題を象徴しているように思えます。
特に中小規模の個別指導塾にとって、これは他人事とは思えません。
むしろ、小さな塾だからこそできる柔軟で創造的な対応が可能な場面とも言えるのです。
そこで今回は、講師の(不満の)声をリスクとみなすのではなく、
塾のブランド資産として活用するという視点で考えてみます。
講師が現場で不満を抱えるのは珍しいことではありません。
しかし、彼らの声を「ただの不満」として処理してしまえば、やがて信頼関係が崩れ、
退職や悪評、あるいは今回のようなストライキにつながるリスクがあります。
一方で、アメリカの調査会社ギャラップが行っている「従業員エンゲージメント」の研究では、
従業員が自らの意見を言える環境にある組織は、
そうでない組織に比べて業績が平均20%以上向上すると報告されています。
つまり講師の声は、自塾に内在する課題を示す貴重なインサイト(洞察)であり、
それを汲み取り運営に活かすことができれば、内部充実の向上にも繋がるはずです。
「共創経営」という言葉があります。
経営者だけでなく、従業員、さらには消費者や取引先、地域社会など、
さまざまな立場のステークホルダーと協力して企業活動をしていくという考え方です。
これに基づいて考えるなら、講師は単なる雇われ労働者ではなく、
共に塾を創り上げるパートナーとして位置づけることができます。
大手の予備校や塾のように組織が巨大化・硬直化し、上意下達(せざるを得ない)体制では、
現場の声を反映するには多くのステップと時間が必要でしょう。
しかし中小規模の塾では、塾長が講師と日常的に接することが多いため、
意思疎通が早く、柔軟に取り組めるという利点があります。
いえ、むしろ最大の強みです。
塾内でのミーティングや講師研修も、
少し発想を変えれば、ブランド開発の場に変えることができます。
例えば講師から指導法や運営改善のアイデアを定期的に募り、
それを「塾の新しい取り組み」として公式ブログやSNSで発信するのも良いかもしれません。
確かに個人塾は、塾長の強烈な個性や理念などが武器になることが多いですが、
「講師発のアイデアを積極的に取り入れる塾」としてのアピールにもなるはずです。
特に保護者さんは、「どれだけ講師が親身か」「塾が進化し続けているか」に敏感です。
講師との共創が「見える化」されれば、
塾の信頼性にも良い影響があるのではないでしょうか。
スターバックスは、パートナー(従業員)の意見を積極的に取り上げ、
商品開発や店舗運営に反映する仕組みを持つことで有名です。
従業員を「パートナー」と呼ぶこと自体がその姿勢を顕著に表していると言えますし、
そうしたブランドイメージが社会的にも広がって、実際に私たち消費者も、
「スタバは従業員を仲間と捉え、共創経営ができる企業」という印象を持っていますよね。
塾でも、「生徒が喜ぶ工夫」や「個々の生徒との関わり方」など、
現場の講師にしか見えない改善のヒントがたくさんあります。
従来、生徒指導の技術などは私たち経営者側が教えることだという先入観がありますが、
講師から学べることもたくさんあるのではないかと思います。
これを経営者が積極的に汲み取り、形にしていけるかが大事なのです。
講師の声を活かすには、単にアンケートを取ったり
ヒアリングをかけたりだけでは不十分です。
実際にそれを実装し、改善として可視化し、
講師にも「自分の意見が塾を変えた」という実感を持ってもらうことが重要だと思います。
講師の提案に対してフィードバックを返す仕組み、
例えば提案に対する実行率と効果報告の共有や、
給与面でのインセンティブに反映するなどの取り組みがあると良いかもしれませんね。
この仕組みが、「講師とともに塾を創る」という文化の土台になります。
講師の声を聞き、取り入れ、実装し、それを社会に発信する――
この循環が、信頼される塾としての存在意義を高めていくのではないでしょうか。
【今回のまとめ】
・講師の意見も塾運営に取り入れてみよう
・取り入れるなら、その姿勢を外部にも「見える化」することが大事