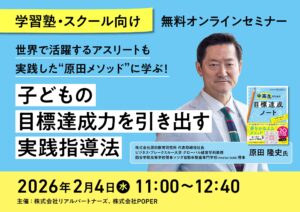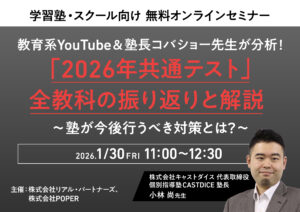今や塾でも学校でも当たり前となった、教育のデジタル化。
導入され始めたころは色眼鏡で見る人も多かったですが、
もはやすっかり定着した感じですね。
かつて日本がICT教育の黎明期だったころ、
世界中からお手本とされてきたのがフィンランドです。
デジタル教育の先進国とされ、
PISAの学力テストでも世界トップクラスの結果を残していました。
ところが近年、そんなフィンランドで「アナログ回帰」が起こっているのだそう。
<デジタル導入の「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化>
記事によると、PISAのテストでも近年は順位が芳しくなく、
その原因を過剰なデジタル化に見出しており、生徒・保護者・教員からも
「教科によっては紙の教科書のほうが良い」という声が多数を占めたとのこと。
こういうニュースを目にすると、塾でも
「やっぱり紙(アナログ)のほうがいいのだろうか……」
「積極的にデジタル教材を導入してきたけど、考え直すべきかも……」
という迷いが生じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
悩ましいところではあると思いますが、
私は、このニュースから学べることが二つあると感じました。
一つは、デジタルかアナログかを二項対立で比較し、
白黒つけようとしないほうがいいのではないかということ。
アナログなツールや作業と相性のいい教科もあれば、その逆もあります。
同じ教科でも単元によって異なるかもしれません。
極端に言えば、例えば美術や図工という教科において、
自分で手を動かして作ることの教育的意義を否定する人はいないでしょう。
そこで「3Dプリンタを使ったほうが早い」とか、
「デザインソフトを使えばもっとキレイな画像(絵)を作れる」というのは論点が違うと思います。
どんなものを作るかというアイデアも、
「AIに聞けば済む」言ってしまえば、人間のクリエイティビティの否定になります。
要は、デジタルかアナログか、それらはあくまで手段でありツールであって、
適材適所で選べばいいということです。
上述のように教科や単元によってもデジタルとの相性は異なりますし、
生徒さんによっても違います。
デジタル教材でサクサク進めたい子もいれば、
歩みは遅くとも「書いて覚える」ほうがやりやすい子だっているはずです。
良くないのは、教育ICTの草創期のようにICTを全否定すること、
逆にアナログを「古い、非効率」だと言って同じく全否定することだと思います。
もう一つは(主張としては似ているのですが)、因果関係を混同しないことです。
今回のニュースでは、フィンランドの学力が低下していることなどを受け、
アナログ回帰が起こっていることを報じています。
しかし、学力低下とデジタルの因果関係がどの程度明白なのかは、よく分かりません。
つまり「学力低下」という好ましくない結果の原因を、
すぐさまデジタルと結び付けて考えるのは危険ではないかということです。
もちろんフィンランドも、デジタルだけが原因だとは思っていないでしょうし、
きっときちんと比較検証した結果だとは思うのですが、私たちがそれを受けて
「そうか、フィンランドのデジタル教育は失敗だったのか。よし、うちもアナログに戻そう」と
脊髄反射的に判断するのは早計ですよね。
それは、デジタルかアナログかの比較だけに限った話でありません。
例えば成績が下がってしまった生徒さんがいたとしましょう。
その原因はテキストなのか、講師の指導力の問題なのか、本人の気持ちの問題なのか、
勉強のやり方の問題なのか、当該単元との個人的な相性の問題なのか、
あるいはそのいくつかが複合的に影響しているのか分からないものです。
逆に成績が上がったとしても、単純に「これのおかげ」とは言えません。
だからこそ、私たちはいろんなアプローチを試行錯誤しているのだと思います。
教育には、特に個別指導においては
「これ!」という唯一解がないのが当たり前だと認識しておくべきではないでしょうか。
振り返って見ると、ICT教育が浸透し始めたころ、否定派の人たちからは
「ICTで学力が向上するというエビデンスを示せ」という声が多く上がっていました。
しかし、初めての試みなのにエビデンスなど示しようがありません。
エビデンスがないからこそ、それを作るためにもやってみるのだとも言えます。
そもそも「ICTで学力が向上するエビデンスを」と言うならば、
アナログだから向上したというエビデンスも必要になりますよね。
エビデンス主義が絶対にダメだとまでは思いませんが、
過剰にそれを信奉しすぎると何もできなくなってしまいます。
やはり「肌感」みたいなものは忘れずにおきたいですし、
それもまたアナログ的な良さだと思います。
学校教育は、長い年月とそこで積み上げられたエビデンスをもとに、
先人たちの試行錯誤の上で、最適化を繰り返しながら作られてきました。
言わば「100%ではないかもしれないけど、現時点ではこれがベスト」だと
思えることを体系化し、提供してきたのです。
でも、「全員でそれをやる」というマス教育においては、そこに合わない子だって出てきます。
だからこそ、個別指導塾というモデルが成立するのではないでしょうか。
「良い教育」とは十人十色であることを具現化したのが個別指導であるとするなら、
その個別指導が「この教え方が正解」「デジタルがいい、アナログがいい」と
決め打ちしてしまうのは矛盾しているとも言えます。
もちろん「こだわり」とはまた別の話ですが、
もっと自由で、もっと自塾らしく、もっと生徒さんに寄り添った教育は作れるはず。
個人塾ならなおさらだと思います。
したがって、デジタルかアナログかという論争も、
不毛とまでは言いませんが、どちらかに結論付けようとしなくて良いと思うのです。
どこか一つ信念や筋を通しながらも、
適材適所、いいとこ取り、臨機応変、そういう柔軟性を持って塾運営をしたいですね。
【今回のまとめ】
・デジタルかアナログかを結論付けなくてもいいのでは?
・何が合うかは人によって違うし、だからこその個別指導塾