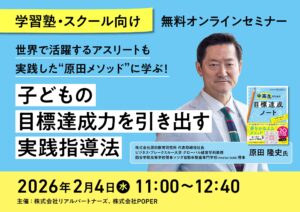先日、ある中学校での痛ましいニュースが報じられました。
持病や発達特性などで配慮が必要な女子生徒について、
教頭が把握していた重要な情報を担任や養護教諭らに十分伝えず、
不適切な指導・対応の結果として生徒が自殺未遂に至ったという事例です。
<学校の不適切対応で女子中学生が自殺未遂 教頭は必要事項を共有せず>
https://www.asahi.com/articles/AST791DVKT79UOOB006M.html
学校現場の深刻な管理問題として報じられましたが、
個別指導塾を経営する立場であっても、これは他人事ではすまされません。
むしろ、生徒さん・保護者さんとの密接な関わりを売りにする個別指導塾だからこそ、
情報伝達不足や誤解は大きな事故や信頼喪失につながります。
しかし、ここから学ぶべきは、「組織内での情報共有が大事」という一般論ではありません。
そんなの当たり前ですものね。
注目すべきは、そもそも保護者さんと塾の間で
「どんな情報を共有する責任があるのか」という期待認識のズレではないでしょうか。
これはマネジメント理論でいう「心理的契約」の問題です。
心理的契約とは、企業側と従業員の間における期待や義務感について、
契約書には明示されない暗黙の了解のことを指します。
顧客との関係においても応用されており、
顧客の期待と企業の提供価値の間に差が生じると「心理的契約違反」となり、
顧客満足度の低下やロイヤリティの喪失につながるというわけです。
要は、お互いに「思っていたのと違う」状態になることだと考えて良いでしょう。
塾においても、保護者さんと経営側の間には「暗黙の了解(期待)」が存在しますよね。
例えば保護者さんは
「子どもの特性や家庭の事情を1度伝えれば、塾側が理解し継続的に配慮してくれるはず」
と期待します。
しかし塾側は「特別な事情は、その都度明確に伝えてもらわなければ分からない」と
考えている場合も少なくありません。
この期待の不一致が、重大なコミュニケーションミスを引き起こすわけです。
今回の学校事例は、教頭が「この程度は伝えなくても分かるだろう」、
あるいは「伝えるほどの情報ではない」と解釈した可能性があります。
同じように塾でも、
「教室長などが面談で聞いた内容を、他の社員・講師も当然知っているだろう」
「保護者さんも、新しい担当者にまた話してくれるだろう」という前提で動いてしまうと、
サポートが途切れてしまいかねません。
こうした心理的契約のズレを埋めるには、塾側から積極的に
「何をどこまで共有するのか」「塾としてどこまで対応できるのか」を言語化して、
保護者さんと合意形成する仕組みが必要です。
具体的には、以下のような実務上の手法が考えられます。
- 「期待されていること」の明示
入塾面談やオリエンテーションの際に、サービス範囲をしっかり説明することが大切です。
保護者さんは「個別指導だから何でも相談しやすい」と期待しがちですが、
塾には法的・専門的に対応できない領域もあります。
「学習面だけでなく、生活面・情緒面の情報も教えていただければ、
学習計画に反映しやすくなります」
「ただし、医療的・福祉的な支援は専門家にご相談いただくことをおすすめします」
といった説明を通じて、役割分担を明確にすることです。
- 「情報更新の責任」を双方で確認する
保護者さんは「以前伝えたから共有されているはず」と思い、
塾側は「新しい情報があればまた言ってくれるだろう」と思います。
このギャップを埋めるには、「情報更新の責任」を共有する約束が必要です。
例えば、定期面談シートやLINE連絡を通じて
・「お子さんの学校の様子や体調面で変化があれば、いつでもご連絡ください」
・「こちらも気づいた点があれば随時お伝えします」
という双方向のコミュニケーション設計を組み込むのです。
これは、医療におけるインフォームドコンセントの概念と似ているかもしれませんね。
医師は、治療にあたって患者に十分な説明をし、意思確認すること、
逆に患者側も、自分の症状などについて正確に報告することで、
信頼関係に基づいた適切な医療ができるという考え方です。
- 契約書や同意書への落とし込み
口頭の約束だけでは認識齟齬が生じます。
・「学習上配慮が必要な特性は、指導担当間で情報共有いたします」
・「ご家庭からの情報提供が不十分な場合、適切な対応ができないことがあります」
などを文書に含めておくことは、保護者さんに過剰な期待を抱かせないためにも有効です。
これにより、心理的契約を「明文化された契約」に近づけることができます。
- 「心理的契約違反」がもたらす経営リスクを認識する
心理的契約理論の研究では、期待していた役割を相手が果たさなかったと感じると、
信頼関係が壊れ、深刻な感情的反発を生むことが分かっています。
保護者さんが「大事なことを塾に伝えたのに、まったく配慮されなかった」と感じれば、
「裏切られた」「ぞんざいに扱われた」という強い怒りや失望を抱くでしょう。
今回のニュースの事例はその最悪の形で、生命の危機にまでつながりました。
塾経営でも「安心して任せてもらう」という価値提供を本気で志すなら、
このリスクを真剣に受け止めなければなりません。
- 経営視点での組織的対応
最後に強調したいのは、これは教室長や講師一人ひとりの
「気配り」に任せてはいけない、という点です。
・入塾時の情報収集フロー設計
・面談時の期待マネジメントの研修
・情報共有ルールの明示
・記録管理(CRMシステム等)の導入
などを組織として整備しなければ、情報ギャップは必ず再発します。
属人的な「ベテラン頼み」を脱し、組織的に期待を調整し続ける
「仕組み」で対応することが大事ではないでしょうか。
今回の学校事例は非常に痛ましいものでしたが、
「教育サービスにおける情報の伝達と期待調整」という根本的課題を浮き彫りにしています。
塾経営者として、この問題を「うちでもあり得ること」と捉え、
「情報共有の徹底」を超えて「心理的契約をデザインする」視点で経営を見直すことが、
信頼の基盤づくりにつながるのではないでしょうか。
【今回のまとめ】
・「言わなくても分かるだろう」では分からないと心得るべし
・心理的契約を目に見える形にする